Greeting理事長挨拶

暑い(熱い)夏です。頻発する自然災害に遭われた皆様と関係者の方々には心よりお見舞い申し上げます。
こうした状況を受けてカーボンニュートラルの実現に貢献すべく太陽光発電の普及拡大を急がなければなりません。
政府が主導する「次世代太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会」も発足しています。
世界の太陽光発電システムの年間導入量は、2017年の約100GWから2023年には400GW超へ、累積導入量は同じ期間で約400GWから1.5TWへと大幅に増加しています。昨秋、UAEのドバイで開催されたCOP28では、各国にエネルギーシステムにおける化石燃料からの「脱却」を求めるとともに、2030年までに再生可能エネルギー導入量を現在の3倍に拡大するという歴史的合意がなされました。
太陽電池材料分野では、p型多結晶シリコンからp型単結晶シリコン、n型単結晶シリコンへと主流が転換しつつあります。さらに、次世代太陽電池として期待されているペロブスカイト太陽電池の実用化も目前に迫っています。特に、ペロブスカイトと結晶シリコンを組み合わせたタンデム型太陽電池は、R&Dレベルでの変換効率が34.6%に達しており、次世代超高効率太陽電池として従来の結晶シリコン太陽電池に代わる高効率太陽電池として期待されています。太陽電池セル・モジュールのサプライチェーンに目を向けると、中国の支配力がさらに増してきています。中国の大規模工場が太陽光発電のコスト低減と普及加速に貢献したことは事実ですが、IEAはリスク分散の観点からサプライチェーンの過度な一極集中に対して以前から懸念を表明しています。米国、欧州、インド、豪州などの大国は、エネルギー安全保障の観点からシリコン太陽電池バリューチェーンを自国内に再構築して、中国への依存度を低減しようと試みています。
日本国内では、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、2040年の電源構成目標を設定する第7次エネルギー基本計画の策定が進められています。ここでもペロブスカイト太陽電池が重要な革新技術の一つとして注目されており、日本政府/経産省はグリーンイノベーション(GI)基金/グリーントランスフォーメーション(GX)政策を通じて、フレキシブルフィルム型やガラス半透明型などのペロブスカイト(単接合)太陽電池の開発を支援しています。しかしながら、これだけではカーボンニュートラルへの貢献も限定的です。風力発電適地の乏しい日本国内において再エネ電力を拡大するには太陽光発電に注力する必要があり、エネルギー安全保障の観点から国内に結晶シリコン太陽電池のバリューチェーンを再構築することも必要です。日本生まれのペロブスカイト太陽電池技術と、高効率結晶シリコン太陽電池技術を組み合わせた超高効率タンデム型太陽電池の技術開発にリソースを割いて挑戦すべきだと考えています。我々PVTECもその一助となるべく、有力企業や研究機関との対話を進めています。
[PVTECの事業]
現在の主力事業は、今年度が最終年度となるNEDOの「太陽光発電主力電源化推進技術開発」における特別事業4件、ならびに今年度開始した経済産業省委託のBIPVに関する国際標準化事業(3カ年)です。NEDO事業4件は、新市場開拓に関する3件(壁面設置PVと移動体PV、PV搭載商用車)と、太陽光発電の長期安定電源化に関する1件です。
NEDO委託事業「壁面設置太陽光発電システム市場拡大のための共通基盤技術の開発とガイドライン策定」は、建物壁面にPVパネルを設置するメリットを定量化、可視化し、ユーザの理解と社会受容性を高めることを目指しています。昨年度末から「壁面設置太陽光発電システム 設計・施工ガイドライン 2023年度版」をWeb上で公開しており(https://www.pvtec.or.jp/data_files/view/367/mode:inline)、2024年度中の改定を目指して論議を進めています。
NEDO委託事業「移動体用太陽電池の動向調査」は、動向調査の枠組で、移動体PVの普及に向けたコミュニティ拡大、レジリエンスなどのメリット評価、信頼性評価技術開発などに取り組んでいます。2023年に新規受託したNEDO委託事業「PV搭載商用車の実証と効果推定技術開発」は、車載太陽電池の発電量を推定し燃料消費低減効果を推定する目的で実証試験を行い検証する事業になりますが、PVTECは委員会を組織し助言を行う等の側面支援を行います。
NEDO委託事業「高安全PVモジュール、高安全PVシステムの技術基準案の策定」では、太陽電池モジュールの火災安全に必要とされる設計基準案策定と評価手法開発に取り組んでいます。また、高安全PVシステムに必要とされる点検、診断技術の技術基準案の策定などに取り組みました。
経済産業省委託事業「建築・構造物一体型太陽光発電に関する国際標準化」は、今年度が受託期間の初年度になり、新規で2つのテーマ、3つのサブテーマをまとめて継続、1つのテーマとして国際標準化に向けて取り組んでいます。
[PVTECの強み]
PVTECの強みは「異分野融合」であり、建築業界との連携に加えて、移動体分野(運輸分野)やIT業界との融合を推進してきました。BIPVに関する各種団体の協議の場所は今やPVTECの重要なミッションとなっており、さらなる発展を目指しています。移動体PVの推進やPV水素の可能性論議なども積極的に進めています。
[PVTECの将来]
戦略企画部会では、PVTECの将来像について議論を継続しています。その中で、ペロブスカイト太陽電池およびペロブスカイト/シリコンタンデム型太陽電池が重要な基軸となっています。2024年5月28日に開催された技術交流会でも、東京大学の瀬川先生と資源総合システムの貝塚様から、ペロブスカイト太陽電池分野の最新技術や産業動向についてご講演いただきました。PVTECは現行の受託事業を着実に遂行するとともに、これらの次世代革新技術についても組合員の皆様と協力し、カーボンニュートラル実現に向けて真摯に取り組んでまいります。引き続きご支援を賜りますようお願いいたします。
2024年8月
太陽光発電技術研究組合(PVTEC) 理事長 永野広作
Overview組合概要
| 組合名(英文名) | 太陽光発電技術研究組合(略称:PVTEC) Photovoltaic Power Generation Technology Research Association |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋五丁目7番1号 久松ビル302号室 |
| 設立日 | 平成2年11月14日(設立総会) 平成2年12月20日(設立認可) |
| 設立の目的 | 組合員各社の研究開発能力を結集し、さらに大学等、産官学の協力のもとで、太陽光発電に関する研究開発を共同で実施し、日本の太陽光発電産業の発展に貢献する。 |
| 研究開発方針 | 本研究組合を通して、国際競争力のある強力な研究開発体制を構築し、研究開発を行う。太陽光発電システムの高性能・高信頼性化技術や健全性維持、新規市場開拓、標準化等の推進に関する共通課題を効率的かつ迅速に解決することにより、日本の太陽光発電関連産業の発展に貢献する。第6次エネルギー基本計画に沿って再エネの主力電源化を推進し、2030年のエネルギーミックスを前倒しできるよう事業化を進める。 |
| 役職員 | 理事長 専務理事 常務理事 |
| 組合員名(五十音順) | 現組合員(2024年7月1日現在、18社・機関)
設立時組合員(23社・機関)
(*印中途脱退組合員) |
| 研究開発の内容 | 太陽光発電産業の健全な市場発展に寄与するために、①建築・構造物一体型太陽光発電に関する国際標準化、②壁面設置太陽光発電システム市場拡大のための共通基盤技術の開発とガイドライン策定、③高安全PVモジュール、高安全PVシステムの技術基準案の策定 、④移動体用太陽電池の動向調査、⑤PV搭載商用車の実証と効果推定技術開発を委託事業として進める。また自主事業として、技術ビジョン研究会/PVへのAI・機械学習応用研究会/PVと金融研究会/タンデムPV研究会/再エネ電力のデジタル取引研究会の5つの研究会にて研究を進める。 |
| 特別事業 |
|
| 自主事業 |
|
| 研究体制 | 理事会、運営委員会のもとで「戦略企画部会」と「技術交流部会」を中心に企画立案、情報交流を行い、委託研究・共同研究を順次スタートさせている。
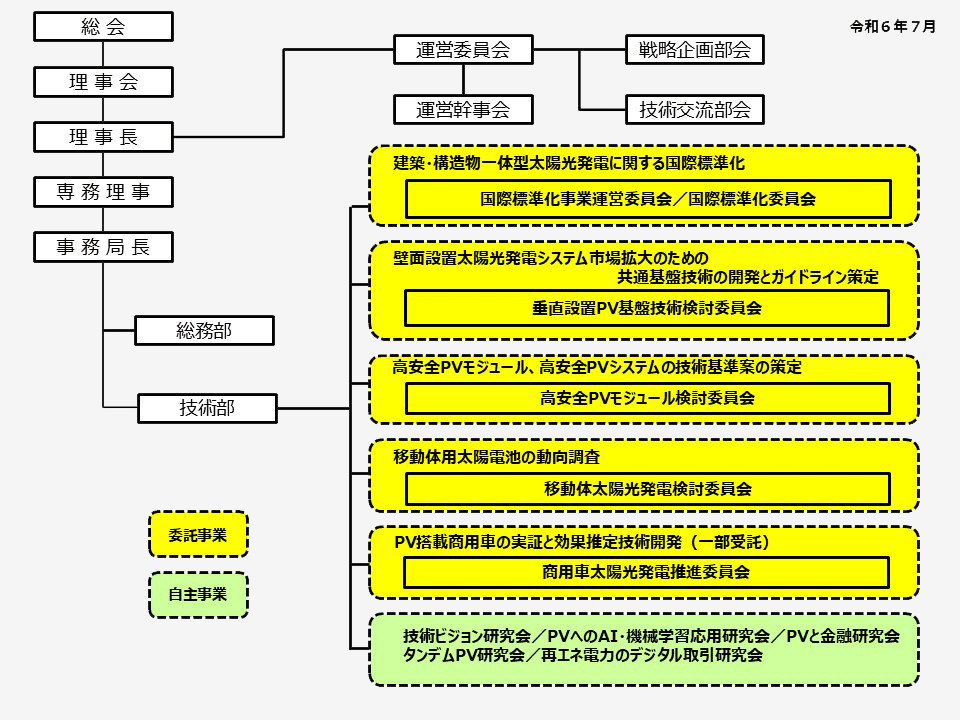 |
Accessアクセスマップ
最寄駅のご案内
JR山手線・京浜東北線「新橋駅」/
都営地下鉄三田線「御成門駅」








